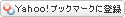「クラウド」とはいったい何か ITベンダーは本質を語れ
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20090701/332996/
面白いところを突いています。
というか、このブログに書きたかったことを先に書かれたというか。
最近、「クラウドコンピューティング、はじめました」的なベンダーが多いですよね。
でも、この分野で先行し、成功しているのはGoogle、Amazon.com、Salesforce.comであり、これらのベンダーは「クラウドコンピューティング、はじめました」ではありません。
あくまで各社が独自に提供するサービスが先に存在し、そのために整備してきたインフラの解放という形態です。
Googleは言わずとしれた検索エンジンやGmailその他。
Amazon.comはECサイト。
Salesforce.comはCRM/SFA。
そういう観点では、Yahoo、mixi、楽天などにはその素養がありますね。
果たして、何を提供するのかが不明なままに「クラウドコンピューティング、はじめました」のベンダー(FとかHとかIとかUとかSとか)がうまくいくのでしょうか?
ここに先鞭を付けるのはMicrosoftでしょうか?
「クラウドコンピューティング、はじめました」がうまくいったら、クラウドコンピューティングの時代は新しいフェーズに入るのかもしれません。
July 6, 2009
クラウドコンピューティング、はじめました
post:
liebejudith
at:
00:44
0
コメント
![]()
labels: Amazon.com, Cloud Computing, Force.com, Google, Google App Engine, IBM, Microsoft, mixi, PaaS, SaaS, Salesforce, Sun, Web2.0, Yahoo
April 20, 2009
沈みゆく太陽
今日はいったい、世界中でどれだけの人がこんなタイトルで
ブログエントリを書いているのでしょうか?
かねてより売却先を探していたSun Microsystemsは
先日報道のあったIBMではなく、Oracleに買収されることが決定したそうです。
オラクル、74億ドルでサンの買収に合意、ハードウェア市場へ進出( Computerworld.jp)
http://www.computerworld.jp/topics/ma/143009.html
オラクル、サンの買収で最終合意(CNET Japan)
http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,2000056020,20391986,00.htm
[速報]オラクルが74億ドルでサンを買収(ITpro総合)
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090420/328819/
[oracle] Oracle、Sunを買収!!!!!(S/N Ratio (by SATO Naoki) by satonaoki)
http://d.hatena.ne.jp/satonaoki/20090420/p2
ラウンドアップ:オラクル、サン買収に至るまでを振り返る
http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,2000056020,20391994,00.htm
米オラクル、サンマイクロを74億ドルで買収へ(Reuters: テクノロジー)
http://jp.reuters.com/article/technologyNews/idJPJAPAN-37591820090420
【速報】オラクルが74億ドルでサンを買収(@IT)
http://www.atmarkit.co.jp/news/200904/20/oracle.html
非常に驚きましたが、ニューヨーカーなビジネスマン集団のIBMよりは
シリコンバレー企業のOracleのほうがずっとしっくりくる組み合わせとも言えます。
プロダクトの品揃えでも、被りよりも補完の要素が多いですし。
特にOracle が欲しいのは、Javaテクノロジのリーダーという地位と
サーバおよびストレージでしょう。
MySQLは微妙な立場ですね。
Oracle DBのシェアを下げた強敵でしたから。
Oracleはオープンソースからは一歩引いた立場と見えるので、
Sunの持っているOSSプロダクトがどうなるか、この先に注目です。
Oracleがこの買収を最大限に活かせれば、向かうところ敵なしですね。
ライバルと呼べるのはIBMぐらいでしょうか。
ハードウェア、データベース、アプリケーションサーバ、
Javaテクノロジ、サーバ仮想化、ビジネスアプリケーション、
クラウドプラットフォーム、OS、SOA・・・
エンタープライズ分野でのソリューションをほぼ全方位カバーすることになります。
しかし・・・
私自身、Sunには多くの知り合いがいる・・・と思っていたら
気がつけば既に退職されている方の方が圧倒的に多いという状況でした。
奇しくも今日もまた、大変お世話になった方がSunを退職されると
ブログに書かれた日でもありました。
(ご本人からは1週間ほど前に聞いていたのですが・・・)
ここ数年は株価(=企業価値とも言い換えられますが・・・)が
下がる一方だったSunですが、数々の業界のカリスマを輩出し、
Javaという一大プラットフォームを築いたSunは
いちエンジニアとして憧れの企業でした。
そのSunが無くなってしまうのは本当に寂しい限りです。
October 19, 2008
Force.comのApex
約1年前に発表されたSalesforce.comが提供するアプリケーション開発環境・動作環境「Force.com」。
Salesforce.comは「SDKを配布するからインストールしてアプリ開発してね」ではなく、アプリケーションの統合開発環境・テスト環境までもWeb上に乗っけてきました。統合開発環境のSaaS化です。アカウントを取得すればブラウザを起動するだけでSalesforce.comのクラウド上でアプリ開発可能です。
しかも既に実用化・収益化できています。Salesforce.comの強みであり、他社がなかなか追いつけない要素の1つでしょう。
はじめて知ったときは、何てスゴイモノを作ったんだ!と驚愕しました。
しかし・・・
プログラミング言語が「Apex」という独自言語なのが惜しいところ。
中身を開けてみればJavaに似ているし、シンプルで覚えやすいのですが・・・
開発者の視点から見るとどんなにカンタンでも「新しい言語を覚えなくてはいけない」というだけで壁が1枚できるものです。
「マルチテナント」と「安全性」を両立するためには、Salesforceのプラットフォームのコア部分が動いているモノ(ここはJavaです)を共有させるわけにはいかず、もう1層上にVM(のようなモノ)を乗っける必要があることは理解できます。
でも、そこがJavaであってもいいはず。
やはり、過去のSunと他社との経緯を無視できなかったのでしょう。
Sunは、Java標準仕様に独自の拡張や独自の制約を設けることに関しては煩いですから。
MicrosoftはJavaに独自の拡張をしたためにSunに訴えられ、長い法廷闘争の末にJava2以降の実装を許されなくなりました。
最近では、GoogleのAndroidも独自のアーキテクチャゆえ、SunとGoogleの間で少し揉めました。
そんなわけで、Sunが進めているProject Carolineには注目しています。SunはProject Carolineで、JavaによるPaaSを実現しようとしています。
Sunの中の人に聞いた限りでは、Project CarolineがSunのクラウドコンピューティング戦略のメインストリームというわけでもなく、SunのPaaSはProject Carolineで行くと決まっているわけでもなく、ただの研究開発プロジェクトの1つでしかない、ということですが・・・
将来的には、EclipseもSaaS/PaaS化したいという噂もちらほら。
Amazon/Oracleあたりで、Xenベースのオープンなアーキテクチャなクラウドコンピューティングという流れもあります。
これらが実用化されたらForce.com/Apexやばいかも。
今はSalesforce.comが先行しています。他社が追いつくまでに時間がかかるので、その間にデファクトを握ってしまおうという方針でしょうか。
それとも、オープンなアーキテクチャへの大幅な方針転換の可能性も視野に入れているのでしょうか。
個人的には、Force.comのプログラミング言語がJavaになってくれたら言うことナシです。
post:
liebejudith
at:
20:32
0
コメント
![]()
labels: Amazon.com, Android, Cloud Computing, Google, Java, Oracle, PaaS, SaaS, Salesforce, Sun
October 5, 2008
最近のクラウド・SaaS・PaaS
Cloud Computing
最近、データセンターを作っただけで「クラウド参入」とか言ってる企業、多くないですか?
「データセンター」を「クラウド」と言い換えているだけのような。
「クラウド・コンピューティング」は「仮想化」以来の“乱用語大賞”
「過大な情報がIT業界に混乱を招く」とガートナーが警鐘
※「MSとIBMが使い出した時点でバズワード化する」とはS社のO氏の発言。(^^;
SaaS
実態はただのWebアプリやASPなのに「SaaS参入」とか言ってる企業、多くないですか?
SaaSと言いながらクラウド環境・マルチテナント環境ではないため、いったいどれだけスケールするのか不安で仕方ない「SaaSもどき」が増えてきました。
PaaS
これを実用化・収益化できている企業はごくわずか。さすがに猫も杓子も「PaaS」と言い出すまでには至っていませんね。
各社の動向
最近の各社の動きはどうなっているのでしょうか?
大きく分けると、
- クラウドインフラのみ提供
- アプリケーションを提供(SaaS)
- アプリケーション動作環境を提供(PaaS)
Yahoo/HP/Intel連合
まだ研究開発段階。クラウドインフラと、もしかしたらPaaSも?
HP、インテル、ヤフーの3社、クラウド・コンピューティングの共同研究プロジェクトを発表
ユニシス
「SaaSはじめます」と言ったが、その後進んでいるのだろうか?「乗り遅れたくない」感で言ってみただけ?
日本における早急なPaaS、CaaSの確立を目指す~ユニシス
富士通
「SaaSはじめました」と言ったが、その後進んでいるのだろうか?「乗り遅れたくない」感で言ってみただけ?
富士通が SaaS 3 サービスを開始
IBM
データセンターをばんばん作っている。その上で何をやるのだろう・・・。クラウドインフラと、もしかしたらPaaSも?
IBM、「Blue Cloud」コンピューティング計画を発表
IBM、世界4カ所にクラウド・コンピューティング・センターを開設
Sun
Project Carolineは大注目。Salesforce.comが成し得ていない、標準言語(Java)によるPaaSを実現しようとしている。でもまだ研究開発段階。
サン、PaaSモデルの研究プロジェクト「Project Caroline」を披露
Google App Engineはアプリケーション実行環境の提供という形式でPaaSをやっているけど、アプリケーションの開発作業はローカルマシン上で行ってそれをアップロードするしかない。
ここ1年ぐらい、エンタープライズ分野では最近目立った動きがないが、Mobile側(Android)からクラウドの使い道を広げようとしている。うまくいけばこっちの切り口からエンタープライズ分野へ食い込んでいけるのかも。
「独創的な」という言葉がぴったりなこの企業の動きには常に要注目。
Amazon.com
インフラの提供はしっかりやっているけど、その上で何をするのか?は利用者任せ。今のところ、Amazon.com自身はECサイト以上のサービスをしていない。Amazon WSは、実質はレンタルサーバっぽい使われ方がほとんどなのでは?
Microsoft
クラウド上にWindows Serverが乗っかって、何が嬉しいのだろうか・・・
MSのクラウドへの取り組みは、Office Suiteにしろ、OSにしろ、結局クライアントパッケージをインストールしないと使えない「非SaaS」なものになるでしょう。
MSのバルマーCEO、「Windows Cloud」の詳細に言及
Oracle
Siebel on Demandなど一部SaaSを提供しているけど、いったいどのぐらい儲かっているのだろうか。MS同様、パッケージライセンスの売上によって過去最高利益を更新し続けているこの企業が、本気でSaaS/PaaSに取り組むとは考えにくい。
Amazon WS上にOracle Databaseを乗っけるパッケージの提供も始めるらしいけど、自社パッケージをクラウドに乗せますという点ではWindows Cloudと同じ。自分でアップロードして展開して設定してね、という点ではもっとひどいかも。すぐに使えるDaaS(Database as a Service)を用意していたらちょっとは「ほう」と思ったかも。
オラクルのクラウドへの第一歩
RedHat
Amazon WS上でJBossが動くようになるらしい。
Red Hatが見据える次世代のアーキテクチャ
Salesforce.com
結局、「クラウドだけどSaaS/PaaSではない」サービスは、ユーザーにとってはハードウェア準備・運用の手間は省けるけど、サーバソフトウェアの構築・管理、アプリケーション開発をしなければならないことは変わらず。MSのアプローチはまた独特だけど。
また、クラウドはそれだけではその存在に意味は無く、クラウド上で提供されるサービスがビジネスとして確立しないと成り立たない。エンタープライズ分野でインフラ・ミドルウェア・アプリケーション・開発環境まで(クラウドからSaaS/PaaSまで)トータルに提供し、実用化・収益化できているのは、事実上SFDCのみか・・・
今のところ、Salesforce.comが独走態勢で、他企業が技術・サービス両面で追いつくのはもう少し先になると思う。
SFDCを脅かすのは、オープン化の波かもしれない。
Amazon WSがXenベースであるため、JBossやOracleは対応できた。
アメリカではAmazon WS互換の他社サービスも始まっているらしい。Amazon WSのバックアップやフェイルオーバー用途に使えるとのこと。
数年後にはプロプライエタリなテクノロジによる囲い込みをオープンソースが切り崩すという波がクラウドコンピューティングの世界にも来るかもしれない。
post:
liebejudith
at:
13:05
0
コメント
![]()
labels: Amazon.com, Cloud Computing, Google, Google App Engine, HP, Intel, Java, JBoss, Microsoft, Oracle, PaaS, RedHat, SaaS, Salesforce, Sun, Yahoo
June 29, 2008
Sun の John Gage 氏が退社
少し前のニュースですが。
J・ゲージ氏、サン・マイクロシステムズを退社--クリーンテクノロジー投資家に転身
http://japan.cnet.com/news/ent/story/0,2000056022,20374980,00.htm
JavaOneで最初に総合司会的役割で登場する、あの John Gage 氏です。
映画俳優のような、渋さとダンディさとかっこよさとオーラのある方でした。
サン・マイクロシステムズ社員のブログでは、Gage 氏が来日・来訪したことは書いていますが、退社したことには一切触れられていないのが、ちょっと不思議な感じがします。惜しむ声があってもよさそうなのですが・・・なにか不文律でもあるのでしょうか。
それとも、自社社員の退社については触れないのが常識?
May 12, 2008
SaaS 普及のカギ
今 SaaS を手がける代表的な企業といえば、Google と SalesForce.com です。
しかし、両社のサービスに私は不満です。
何がって?
SaaS Office Suite
(残念ながら?)世の中の人々(特に企業ユーザー)は、MS Office を手放せません。SaaS ドキュメントにも MS Office 完全互換を求めています。
Google Document が MS を打倒できない理由は、ズバリ MS Office 完全互換でないからです。一応 MS Office 形式でエクスポートは可能ですが、マクロは動作しないし、レイアウトが崩れたりします。
OOo の普及が進まないのも、MS Office 完全互換ではないからという理由に他ならないからでしょう・・・
MS さん!何やってるんですか?
Office ドキュメントと Web 上のドキュメントのインポート/エクスポートを完全に行える SaaS 形式の Office Suite をリリースすればみんな使うのに・・・
結局、最終的にはローカルへのインポート/ローカルからのエクスポートの需要はあるのだから、ユーザーが増えれば(減らなければ)Office は売れ続けるのに・・・
マクロも消えない、完全互換の SaaS ドキュメントは(現在のところ) MS だけが作れるものなのに・・・
「オープンである」とかはきれい事。特に企業ユーザからは MS Office 完全互換が求められているのが事実だと思います。
Web にインポート/エクスポートできる MS Office ドキュメントは厳密に言えば SaaS ではないのですが、ユーザが求める物を提供することは大事ですよね。
クラウド/ PaaS
SalesForce.com の Force.com は Apex という独自言語と独自 API がネックですね。他のプラットフォームへ移植できませんから。
Google App Engine も、同じ理由で Bigtable がネックです。
Sun さん!何やってるんですか?
完全 Pure Java なクラウド環境をリリースすればみんな使うのに・・・
Glassfish が使えて、H2 や Derby (JavaDB) が動作すれば言うことナシです。
Google App Engine なんてメじゃないのに・・・
完全 Pure Java なクラウド環境がリリースされれば Java テクノロジはますます躍進するでしょう。そして、Sun は PaaS 分野のリーダーとなれるでしょう。
・・・とここまで書いて思い出しました。たしか、Sun は非営利団体等へ仮想化サーバスペースを無償で提供するというソリューションをやっていたはず。・・・
ただし、米 Sun のサービスで日本語文字コードセットの扱いに問題があったような。
具体的な資料は探し出せず。。。残念。
Web メール
SaaS の普及がもっとも進んでいる分野が Web メールでしょう。Gmail、Hotmail (Windows Live! Mail)、Yahoo! Mail を利用している人はとても多いと思います。
しかし、メインではメーラーによる POP アクセスが主で、Web メールの利用はプライベートでは 30%、ビジネス利用では 10% 以下です。(2007年9月の記事による)
Web メールメイン利用、仕事では約9%・自宅では約30%
http://japan.internet.com/research/20070920/1.html
Web メールの利用はセカンドアドレスや「漏洩・流出してもかまわない、いざとなったら捨てられるアドレス」としての利用が大多数なのではないでしょうか。企業ユースではさらに比率が下がりますが、これは情報漏洩対策等の結果でしょう。
SaaSを使わない理由
こんな記事もありました。
SaaSを使わない理由――IT投資調査から
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0805/14/news015.html
それなりに多いSaaS普及への課題
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0804/25/news007.html
May 8, 2008
MySQL、新機能のクローズトソース化の決定を撤回
先月、「MySQL、新機能追加は有償版の「MySQL Enterprise」だけを対象に」という記事が Technobahn より出て、Sun が各方面の OSS 支持者の非難を浴びるという事件がありました。
MySQL、新機能追加は有償版の「MySQL Enterprise」だけを対象に
http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200804172000
こんな苦しいフォローもありましたが・・・
「一部報道で、MySQLに対する今後の新機能追加は有償版である「MySQL Enterprise」のみに適用されるとあり、これがコミュニティーから強い不快感を招いているが、実際には、「一部」の機能やドライバがMySQL Enterpriseにのみに搭載されるという趣旨である。」
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0804/21/news118.html
やっぱりこうなりましたね。
MySQL、新機能のクローズトソース化の決定を撤回
http://www.technobahn.com/news/2008/200805071431.html
クローズドソース化は MySQL の方針で、Sun の意向に反する(と主張している)ところが引っかかりますが・・・
ベンダーのオープンソース戦略の難しさを感じさせる一件だと思います。
オープンソースと言えば Linux カーネルや、Apache Software Foundation だった時代は、「オープンソース=有志によるボランティア活動」という色も強かったのですが、IBM の Eclipse が普及してきた頃から、ソフトウェアベンダーが自社製品をオープンソースライセンスで公開するという動きが急速に広まってきました。
しかし、中にはこの戦略がうまくいっていないベンダーがあります。
営利企業である以上、すべての事業は自社の収益に結びつけられるべきなのですが、オープンソース戦略はいかに大きい目・長い目で見て、業界全体が育っていくのを見守れるかにかかっていると思います。
一気にシェアを取りに行ったり、ライバルを意識して業界内での存在感をアピールしようとしたり、短期的な収支を考えたりという理由で焦ってもいいこと無いですね。
April 18, 2008
MySQL、新機能追加は有償版の「MySQL Enterprise」だけを対象に
MySQL、新機能追加は有償版の「MySQL Enterprise」だけを対象に
http://www.technobahn.com/news/2008/200804172000.html
「MySQLは16日、米カリフォルニア州サンタクララで開催中のMySQLコンファレンスの席上で今後の新機能追加は有償版の「MySQL Enterprise」だけを対象としていく方針を明らかにした。」
「無償版の「MySQL Community Server」の提供は今後も継続されるが、無償版と有償版の開発は完全に切り離されることとなり、無償版と有償版の2つのMySQLはまったく別々の進化を遂げることとなる見通しだ。」
※technobahn のサイトが落ちているようなので、Google のキャッシュをご利用下さい。
Sun Microsystems の恐るべき愚行と言えます。
このニュースは、いったいどれだけの OSS 支持者を失望させ、どれだけの OSS 支持者の反感を買うのでしょうか?
今日六本木ミッドタウンで行われていた Sun Business .Next 2008 や G.W.明けの S.F.で行われる JavaOne 2008 で、オープンソース団体による抗議デモが行われても不思議ではないぐらいです。
今回発表されたこの方針に変更が無い限り、MySQL を離れるユーザは増加の一途をたどることでしょう。
こうだったはずなのに・・・
http://japan.cnet.com/news/ent/story/0,2000056022,20371630,00.htm
「Sunは、次バージョンMySQLの「ファイナルに近い」ビルドを公開するとともに、1月に10億ドルで買収した同オープンソースデータベース企業の文化を変更しないことを約束した。」
http://japan.cnet.com/news/ent/story/0,2000056022,20371536,00.htm
「Sun MicrosystemsがMySQLを10億ドルで買収した際に浮上した最大の問題は、両社の明白な文化的衝突だろう。長年、クローズドソース企業としてやってきたSunがオープンソース企業のMySQLを買収したことで、オープンソースコミュニティーの一部から、今後の成り行きを懸念する声が上がった。しかし、Sunは米国時間4月15日、買収をめぐるあらゆる疑問を払拭すべく、1月に買収が完了して以来、初となる大規模なMySQL開発者向けの集会MySQL Conference & Expoで、両社の相思相愛ぶりを演出した。」
January 17, 2008
Oracle, BEA, Sun, MySQL
OracleがBEAを買収しました。
Oracle to Acquire BEA Systems
http://www.oracle.com/corporate/press/2008_jan/bea.html
一度はBEA側が金額面の理由(67億ドル)で拒否したのですが、
とうとう85億ドルで合意に至ったようですね。
SunがMySQLを買収しました。
Sun to Acquire MySQL Press Kit
http://www.sun.com/aboutsun/media/presskits/2008-0116/index.jsp
こちらも私には意外に思えるニュースです。
SunはどちらかというとMySQLよりもPostgreSQLと親密だと思っていたので・・・
昨年の Sun Tech Days Tokyo 2007 でも PostgreSQLのブースが出展されていました。
SunはLAMPの"M"を自社DBブランドとして手に入れたことになりますね。